大学入学共通テスト(地理歴史) 過去問
令和6年度(2024年度)追・再試験
問91 (<旧課程>地理B(第5問) 問2)
問題文
アキラさんは、入間市付近の丘陵にみられる森林に関心をもった。次の写真1は、この地域の雑木林の景観を撮影したものである。また、後の文章は、この地域の雑木林の役割や利用方法についてアキラさんがまとめたものである。文章中の下線部Eの事例は後の文カとキのいずれか、下線部Fの事例は後の文aとbのいずれかである。EとFの事例を示した文の組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
写真1のような雑木林は、E 1960年代頃まで主に地域住民によって利用されてきたが、社会や経済の変化により、従来の役割を失った。その後、この地域の雑木林は都市開発の対象とされたが、最近ではF 雑木林を保全し、利活用する動きがみられる。
Eの事例
カ 幹や枝、落ち葉を利用して、薪(まき)や炭、堆肥が作られた。
キ 幹を切り出して、住宅向けの規格化された建材として利用された。
Fの事例
a 外国産の成長の速い樹木を植栽し、地球温暖化対策を進める。
b 草刈りイベントを開催し、参加者の雑木林への関心を高める。
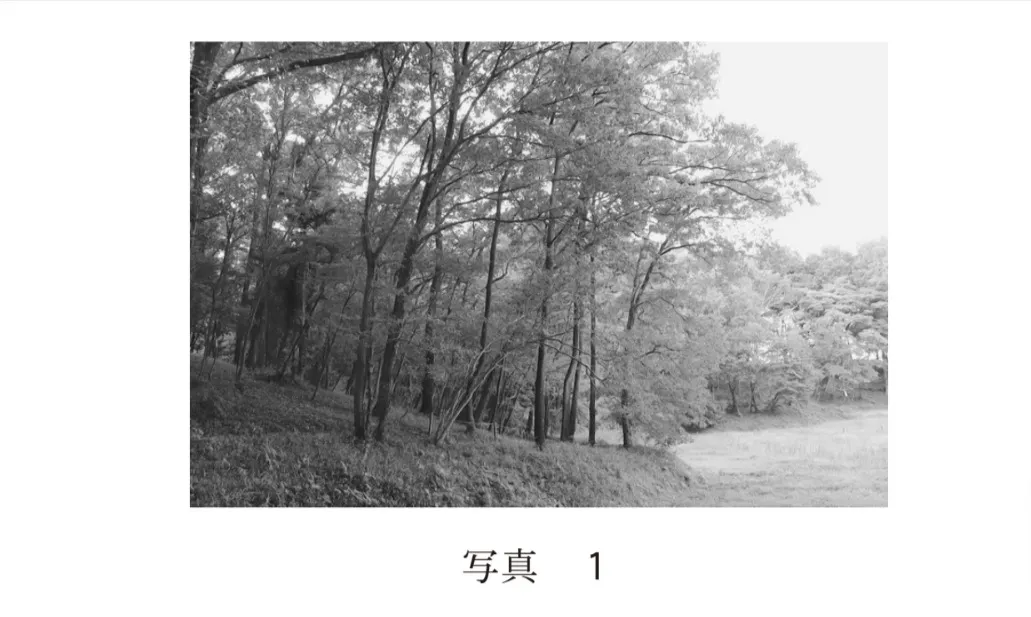
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
大学入学共通テスト(地理歴史)試験 令和6年度(2024年度)追・再試験 問91(<旧課程>地理B(第5問) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
アキラさんは、入間市付近の丘陵にみられる森林に関心をもった。次の写真1は、この地域の雑木林の景観を撮影したものである。また、後の文章は、この地域の雑木林の役割や利用方法についてアキラさんがまとめたものである。文章中の下線部Eの事例は後の文カとキのいずれか、下線部Fの事例は後の文aとbのいずれかである。EとFの事例を示した文の組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
写真1のような雑木林は、E 1960年代頃まで主に地域住民によって利用されてきたが、社会や経済の変化により、従来の役割を失った。その後、この地域の雑木林は都市開発の対象とされたが、最近ではF 雑木林を保全し、利活用する動きがみられる。
Eの事例
カ 幹や枝、落ち葉を利用して、薪(まき)や炭、堆肥が作られた。
キ 幹を切り出して、住宅向けの規格化された建材として利用された。
Fの事例
a 外国産の成長の速い樹木を植栽し、地球温暖化対策を進める。
b 草刈りイベントを開催し、参加者の雑木林への関心を高める。
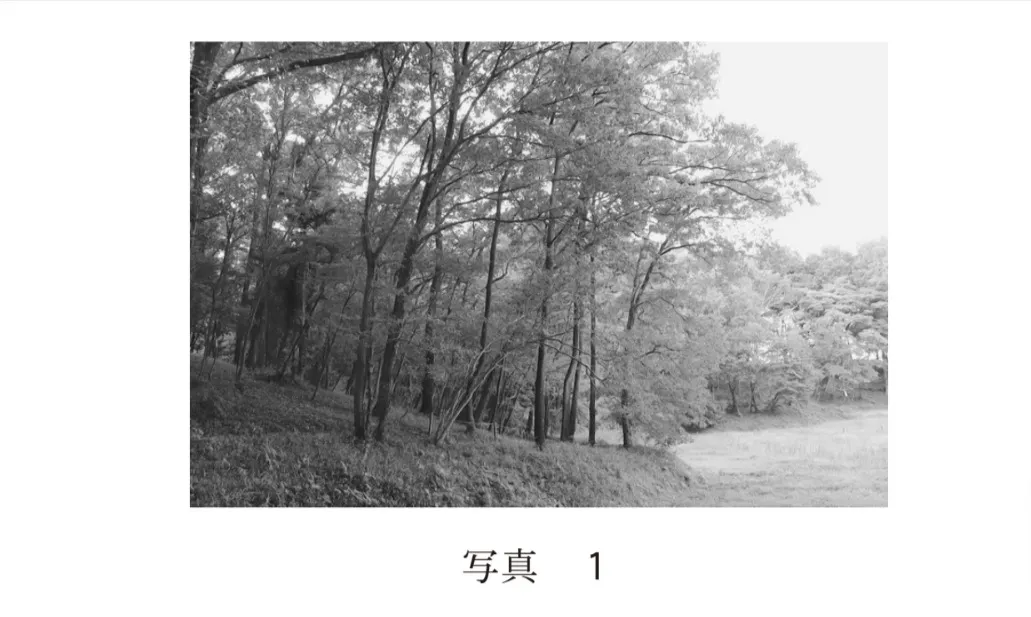
- カ ― a
- カ ― b
- キ ― a
- キ ― b
正解!素晴らしいです
残念...

この過去問の解説 (1件)
01
今回の問題のポイントは文脈と事例が適切かどうか考えると答えを導くことができます。
〈Eの事例に関して〉
カ:幹や枝、落ち葉を利用して、薪(まき)や炭、堆肥が作られた。
→1960年代のエネルギー革命で石油が燃料として使用されるまで、雑木林の樹林は薪や炭として燃料に使われ、落ち葉は畑に入れる堆肥として利用されていました。そのため、カは適切です。
キ:幹を切り出して、住宅向けの規格化された建材として利用された。
→住宅用の建材はスギやヒノキなどの人工林を利用されているため、雑木林のような植生の豊富な素材を建材に利用することは考えにくいです。そのため、キは不適切です。
〈Fの事例に関して〉
a:外国産の成長の速い樹木を植栽し、地球温暖化対策を進める。
外国産の樹木は植栽することは、人工林の減少を抑制するための施策ですので、雑木林を保全する旨の文章としては不適切です。
b:草刈りイベントを開催し、参加者の雑木林への関心を高める。
近年、小中高の学習プログラムに自然環境を体験する学校のイベントに参加する体験することが増えています。このように、地域住民が草刈りイベントや環境学習を通じて雑木林の保全活動に取り組むことが増加しています。そのためbは適切です。
以上より、カ-bが適切です。
誤りです。
正しいです。
誤りです。
誤りです。
どの選択肢も文章としては正しいものですが、文脈に沿っているかどうかを判断する必要があります。雑木林について適切な文脈で書かれているか分かれば適切な回答を導くことが出来ます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問90)へ
令和6年度(2024年度)追・再試験 問題一覧
次の問題(問92)へ